「分からせ×純愛=メス堕ち〜反転アンチで冷笑系フェミ落ちした女子を、分からせと純愛でメス堕ちさせましょう〜」
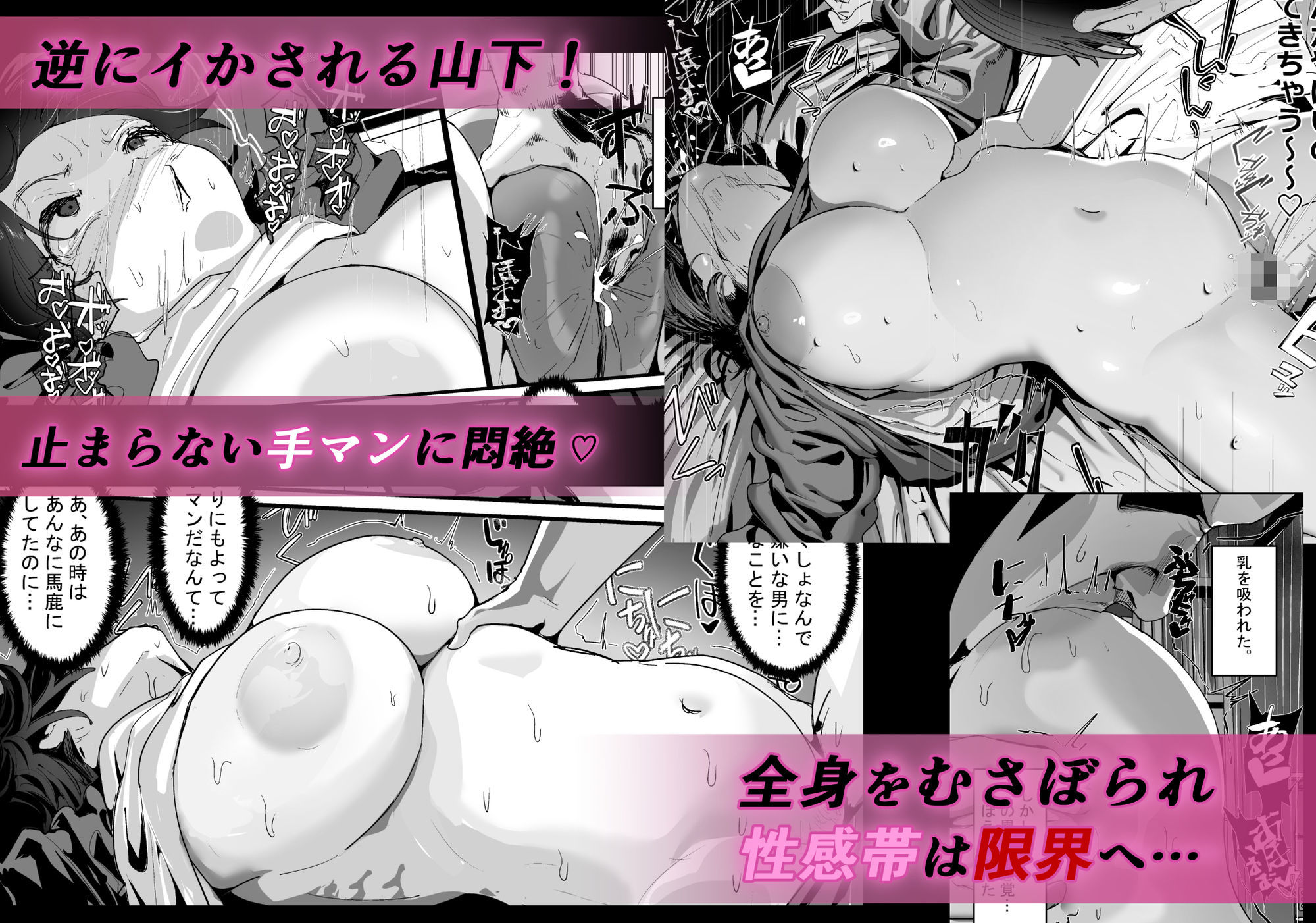


「分からせ×純愛=メス堕ち〜反転アンチで冷笑系フェミ落ちした女子を、分からせと純愛でメス堕ちさせましょう〜」
==============================
〜3枚の怪奇な写真。
1枚目はまだ小学校低学年くらいの、頬に泥をつけて笑ってる純朴な女の子。
2枚目は二十歳を過ぎたばかりの、短く切った髪に無表情、SNSで男を罵ってるスクショが一緒に貼ってあるボーイッシュな姿。
でも3枚目がほんとにヤバい。同じ女が、頰を赤らめて目を潤ませ、甘ったるい声で「ごめんなさい」って言ってるみたいな、まるで別人の写真。
たった一年でここまで変わるなんて、ちょっと信じられないよね。〜
俺が彼女、佐藤灯花(とうか)と出会ったのは、去年の秋だった。
大学のサークル合宿で、フェミニズム系の読書会みたいなのに顔を出したら、そこで一番声がデカかったのが彼女だった。
「男ってさ、結局自分の都合しか考えてないよね」
そう言いながら、俺の顔をチラッとも見ない。
なんかムカついたから、つい口を挟んだ。
「都合って言うけど、君が今着てるスニーカーも、スマホも、男が作った工場で安い賃金で働いてる女の人たちが支えてるんだよ?」
そしたら灯花、初めてこっちを見た。
目が鋭くて、笑ってるのに全然笑ってない。
「へえ、男のくせにそういうこと言うんだ。珍しいね」
その日から、俺たちは犬猿の仲になった。
SNSでもバチバチやり合ってた。
灯花のアカウントは「@anti_men_forever」みたいな感じで、毎日男叩き投稿。
俺はわざと煽るリプライを送る。
「男が全員クズなら、君の父親もクズ?」
「父親? あんなの精子提供者でしかないよ」
みたいなやり取りが、フォロワーたちのエサになってた。
周りは「またやってるw」って冷やかしてたけど、俺はだんだん本気で腹立ってきた。
いや、腹立つのと同時に、なんか妙に気になってた。
灯花の投稿って、どれもこれも「男なんて要らない」って言いながら、妙に執着してる気がして。
まるで、男に傷つけられた経験を必死に忘れようとしてるみたいだった。
ある日、俺がバイト先のカフェでシフト入れてたら、灯花が入ってきた。
一人で。ノートPC開いて、なんか執筆してるっぽい。
俺、わざと声かけた。
「いらっしゃいませ。いつものブラックコーヒー?」
「……なんで知ってるの」
「君、毎回同じの頼むじゃん。俺ここでバイトしてるし」
灯花、顔をしかめたけど、席に座った。
閉店間際、客が誰もいなくなって、俺は灯花のテーブルにコーヒーおかわり持っていった。
「サービス」
「……いらない」
「いいじゃん、奢りだよ」
灯花、ため息ついて受け取った。
その瞬間、俺、気づいたんだ。
灯花の手が震えてる。
コーヒーカップ持つ指が、微かに震えてる。
「寒いの?」
「……関係ない」
「なんか疲れてるみたいだね」
灯花、急に黙った。
そして、小さく呟いた。
「最近、寝れてないんだよね……」
理由を聞くと、SNSで叩かれすぎてメンタルやられてるらしい。
灯花の投稿が過激すぎて、逆にフェミ叩きのアカウントから集中砲火浴びてた。
「男なんて死ねばいいのに」みたいな投稿がバズっちゃって、炎上。
「でもさ、それって君が望んでた反応じゃないの?」
俺が言うと、灯花、俯いた。
「……わかんない」
初めて見た。灯花の弱いところ。
それから、少しずつ話すようになった。
最初はカフェの閉店後だけ。
灯花、だんだん素を出してくる。
「私、小さい頃、お父さんに捨てられたんだよね」
「母親はいつも男連れてきて、私のことなんて見てくれなかった」
「だから男って信じられない」
俺、黙って聞いてた。
ただ、時々相槌打つだけ。
灯花は話してるうちに泣きそうになってた。
「でもさ、こんなこと誰にも言ったことないのに……なんであんたに話してるんだろ」
俺、笑った。
「俺が安全だからじゃない?」
「は?」
「だって俺、君のこと叩いてたけど、本気で傷つけようとは思ってなかったもん。ただ、君の鎧が厚すぎて、剥がしたくなっただけ」
灯花、目を丸くした。
「鎧?」
「うん。君、めっちゃ強がってるけど、本当は寂しいんでしょ?」
灯花、黙ってコーヒー飲んだ。
カップが空になるまで、何も言わなかった。
冬になると、灯花は少し変わった。
髪を伸ばし始めた。
メイクも、ちょっとだけするようになった。
SNSの投稿も減った。
俺と会う回数が増えた。
夜の公園で、缶コーヒー片手に話すのが日課みたいになった。
「ねえ、私ってさ……変かな」
「変じゃないよ」
「でも、前と全然違う」
「それが悪いこと?」
灯花、首を振った。
「わかんない……なんか怖い」
「何が?」
「自分が、自分じゃなくなっちゃうのが」
俺、灯花の手を握った。
冷たかった。
「俺は、どんな灯花でも好きだよ」
灯花、びくっとした。
「……嘘」
「本当だよ」
灯花、顔を赤くして俯いた。
その日から、灯花は俺のことを避けるようになった。
LINEも返ってこない。
カフェにも来ない。
一ヶ月後、俺の部屋のチャイムが鳴った。
開けたら、灯花が立ってた。
髪は肩まで伸びてて、ワンピース着てた。
「……ごめん」
いきなり土下座された。
「私、逃げてた」
「灯花……」
「あんたのこと、考えるだけで胸が苦しくて……でも、会いたいって思って……」
灯花、泣いてた。
俺、灯花を抱きしめた。
「もういいよ」
「でも私、ひどいこといっぱい言った」
「知ってる」
「ごめんなさい……ごめんなさい……」
灯花、俺の胸に顔を埋めて泣き続けた。
その夜、灯花は帰らなかった。
朝、目が覚めたら、灯花が俺のTシャツ着て、キッチンで卵焼いてた。
「起きた?」
「あ……うん」
「ちゃんと食べなきゃダメだよ」
灯花、笑ってた。
昔の冷笑とは全然違う、柔らかい笑顔。
俺、思わず抱きしめた。
「え、ちょっと、朝から……」
「灯花」
「なに?」
「好きだよ」
灯花、目を潤ませて、俺の胸に額を押し当てた。
「……私も」
その瞬間、俺、確信した。
灯花は、もう戻らない。
あの冷笑系のフェミだった灯花は、もういない。
代わりに、俺の前で甘えてくる、ちょっとわがままで、すごく可愛い灯花がいる。
それから一年。
3枚目の写真は、俺が撮った。
灯花が俺の膝の上で、頰を赤らめて「もう……意地悪しないでよ」って言ってる写真。
昔の灯花を知ってる人たちは、みんな驚く。
「え、灯花ちゃんってあんな子だったの!?」
って。
俺、内心で笑ってる。
だって、あの鎧を剥がしたの、俺なんだもん。
分からせと純愛で、完璧にメス堕ちさせたんだもん。
灯花は今、俺の前じゃ素直すぎて困るくらい。
「ねえ、今日も一緒に寝て?」
「灯花、俺明日早いんだよ」
「えー、だっていまは私が一番大事なんでしょ?」
「……まあ、そうだけど」
「じゃあ、いいよね♡」
もう、完全に手の中。
でも、それが幸せなんだ。
灯花が俺だけを見てくれるのが、俺の全部なんだ。
〜fin〜


