「メス堕ちお姉ちゃん〜いつも守ってくれた男勝りなお姉ちゃんは今日も先輩に抱かれてオンナになる〜」

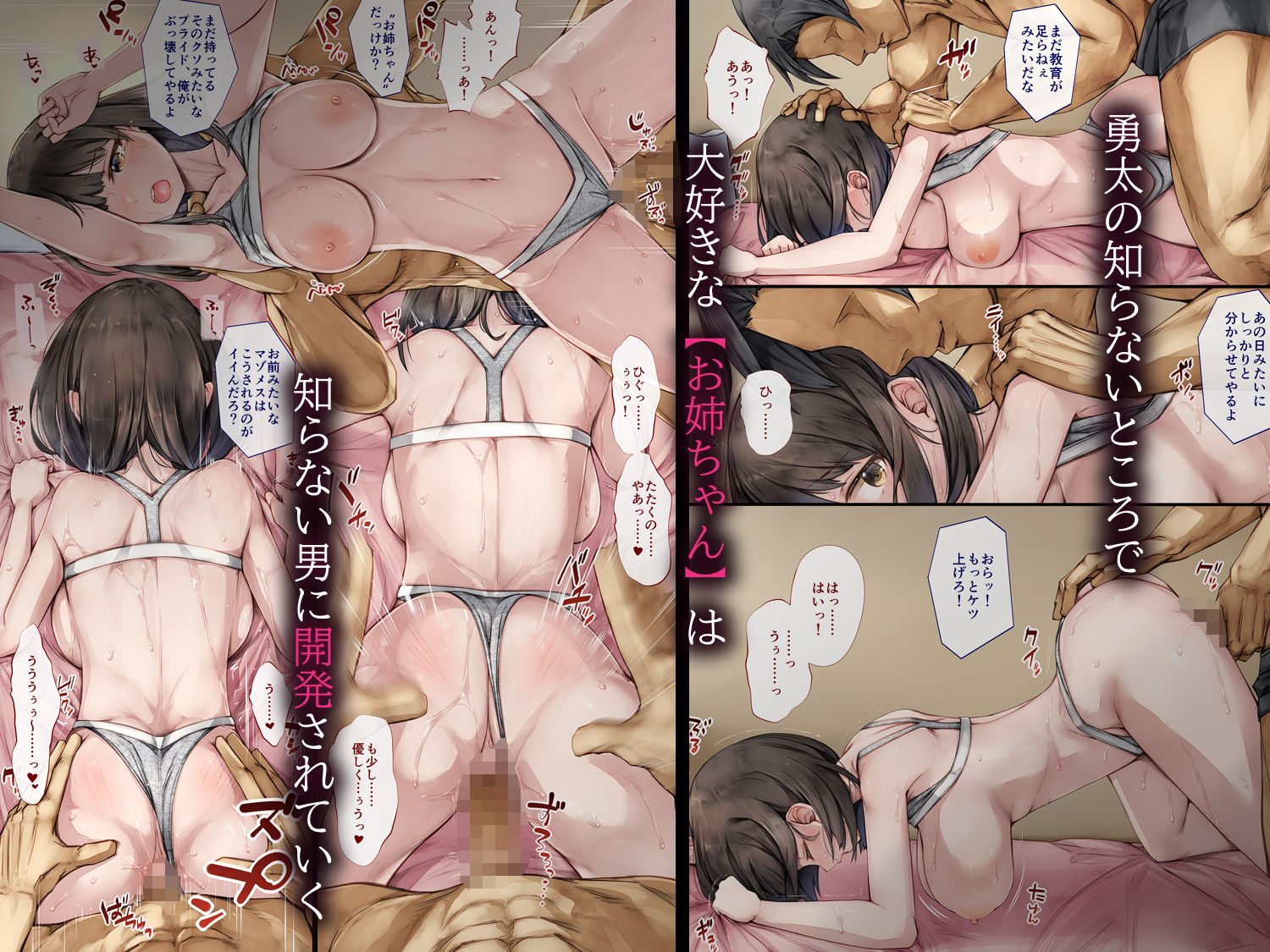

「メス堕ちお姉ちゃん〜いつも守ってくれた男勝りなお姉ちゃんは今日も先輩に抱かれてオンナになる〜」
==========================
いつも僕を守ってくれるかっこいいお姉ちゃん。
いつか僕が、お姉ちゃんのことを守ってあげられるようになりたい。
──そう思っていた。
幼い頃から、須堂涼華は僕のヒーローだった。男勝りで活発な彼女は、困っている人がいると決して見過ごせないお人好し。真面目で面倒見がよく、いつも‘良きお姉ちゃん’であろうと自分を律してきた。僕、百合島勇太とは一歳差の幼馴染で、家族同士の付き合いも深い。生まれつき体が弱く、激しい運動ができない僕は、幼少期に何度もいじめの標的になった。そのたび、涼華が駆けつけて守ってくれた。彼女は僕のために武術を習い始め、華奢な体躯からは想像もつかないほどの強さを身につけた。弟同然に大切に思ってくれる涼華に、僕は心から感謝し、いつか恩返しをしたくてたまらなかった。いや、それ以上に──彼女に想いを告げたいと思っていた。でも、勇気が出なくて、折に触れては先延ばしにしてきた。
そんな穏やかな日々が、廃倉庫での出来事を境に変わり始めた。あの日、涼華は地元の不良グループとの話し合いに赴いた。僕は心配でたまらなかったが、彼女の決意は固く、僕の制止を振り切って出かけて行った。後で聞いた話では、グループのリーダー格が近隣のトラブルを起こしていて、涼華は一人で交渉に臨んだのだ。彼女の正義感がそうさせたのだろう。話し合いは無事に終わり、涼華は少し疲れた様子で帰宅した。でも、それから彼女の変化は目に見えて現れた。
これまでショートカットで、動きやすいジーンズとTシャツが定番だった涼華が、急に髪を伸ばし始めた。サラサラと肩まで伸びた黒髪が、風に揺れる姿は新鮮で、どこか大人びて見えた。服も変わった。活発さを象徴するパンツスタイルから、ヒラヒラしたスカートや柔らかなブラウスへ。鏡の前でくるりと回ってみせ、「どう? 似合うかな」と照れくさそうに笑う彼女。みるみるうちに、男勝りな少女から、優雅で魅力的な女性へと変わっていく。僕は戸惑った。嬉しいような、寂しいような──。この変化の理由を尋ねても、涼華は「たまには女の子らしくしてみようかなって」と、曖昧に微笑むだけだった。心のどこかで、彼女が大人への一歩を踏み出しているのを感じ、僕の胸はざわついた。いつか守ってあげたいと思っていたのに、ますます置いていかれそうな気がした。
そんなある夏の日、蒸し暑い陽射しが照りつける午後、僕はいつものように涼華の家に遊びに行った。家族同士の付き合いが深いせいで、僕の家から徒歩五分の距離。チャイムを鳴らすと、涼華の母さんが笑顔で迎えてくれた。「涼華、勇太くんよー!」と声をかけると、階段を降りてくる足音がした。そこに現れたのは、涼華と、もう一人──見覚えのある男。以前、廃倉庫の話し合いの場で一度だけ会った、不良グループの一員、剣崎健吾だった。
健吾は長身で、鋭い目つきが印象的な二十歳。地元で名の知れた不良だが、利己的で自分の欲求に忠実な性格だという噂を耳にしていた。確かな腕っぷしがあり、それを利用しようと周りが勝手に集まってくるが、本人は他人とつるむのを好まないらしい。あの廃倉庫で涼華と対面した時から、彼女に興味を持ったようだ。家の中に入るなり、健吾は僕を値踏みするように見つめ、ニヤリと笑った。「おい、君が勇太か。涼華の大事な幼馴染だろ?」その声は低く、威圧的だった。涼華は少し慌てた様子で、「健吾くん、何しに来たの?」と尋ねたが、彼は平然とソファに腰を下ろした。
話の流れで、健吾は半ば強引に僕の連絡先を聞き出し、スマホに登録した。「これでいつでも連絡取れるな。邪魔はしないよ、約束する」と言いながら。僕は居心地の悪さを感じつつ、涼華の様子を窺った。彼女は少し頰を赤らめ、視線を逸らしていた。その直後、僕のスマホが震えた。健吾からのメッセージ──動画付きだった。好奇心と不安が入り混じり、僕はそっと再生した。
画面に映ったのは、目の前にいるはずの二人、涼華と健吾。廃倉庫の薄暗い照明の下で、親密に寄り添う姿。涼華の長い髪が揺れ、ヒラヒラの服が優しく翻る。健吾の大きな手が彼女の肩を抱き、互いの視線が絡み合う。動画は二人の特別な瞬間を捉えていた──穏やかで、情熱的な時間。僕の心臓が激しく鳴った。涼華が、僕の知らない世界に足を踏み入れている。守ってあげたいと思っていたのに、彼女はもう、別の誰かに守られているのかもしれない。動画が終わると、健吾が僕を見て言った。「見ただろ? 涼華はもう、大人の女だよ。お前も、そろそろ諦めろ」
僕は言葉を失い、ただ立ち尽くした。夏の陽射しが、部屋を容赦なく照らす中、僕の想いは砕け散りそうだった。それでも、心の奥で、涼華への気持ちは消えなかった。いつか、僕が彼女を守れる日が来るのか──。その答えを探す旅が、今、始まったばかりだった。


