「皇帝の指南役 -クールな女官の筆おろし子作り指導-」
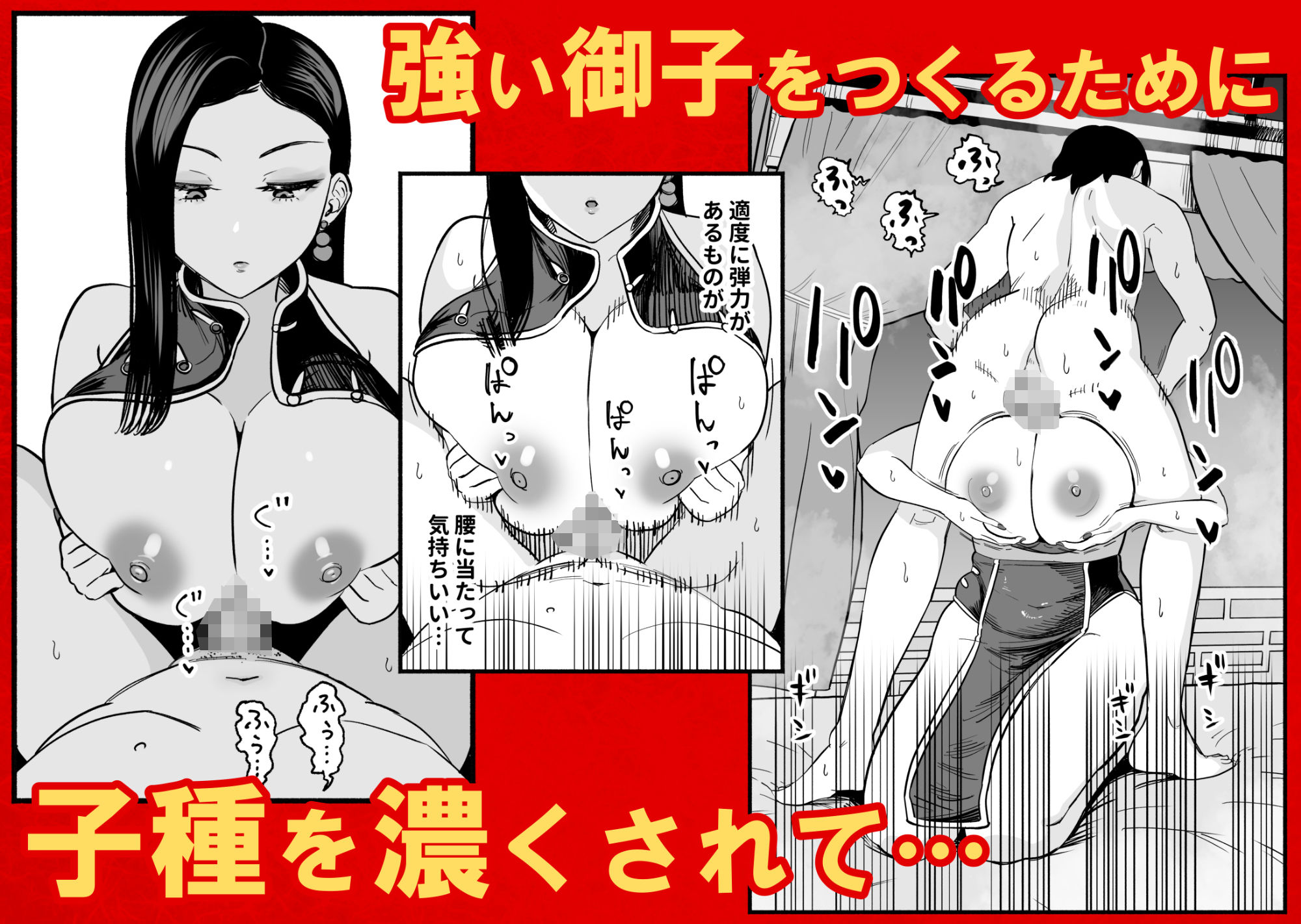


「皇帝の指南役 -クールな女官の筆おろし子作り指導-」
========================
皇帝の指南役
~クールな宮女の筆おろし子作り指導~
紫禁城の奥深く、宸襟の間はいつもひんやりとしていた。
秋の風が絹のカーテンを揺らす頃、俺はもう二十歳を越えていた。
一国の皇帝として即位して三年。政務はなんとかこなしているが、夜の帳が下りるたび、胸の奥に重い影が落ちる。
後宮は三百人を超える美女で溢れているのに、俺はまだ誰の体も知らない。
女人の柔らかさも、熱も、匂いさえも、まるで他人事だった。
そんな俺を憐れんだのか、太皇太后の命で、ある女が遣わされた。
その夜、燭台の灯りだけが頼りの寝殿に、静かな足音が近づいてきた。
「……失礼いたします」
現れたのは、宮廷女官のメイリン。
黒髪を高く結い上げ、薄紫の袍に身を包んだ姿は、まるで夜の闇に溶けるように涼やかだった。
年齢は二十代半ばだろうか。切れ長の瞳は氷のように澄んでいて、俺を見据える視線に一切の甘さがない。
彼女は膝を折り、丁寧に額を床に擦りつけた。
「今夜より、陛下のお相手を務めさせていただきます。子作りの心得を、しっかりとお教えいたします」
声は低く、どこか諦めたような響きを帯びていた。
俺は言葉を失った。
これまで側近の宦官たちが遠回しに「そろそろ……」と匂わせてはいたが、まさかこんな形で、しかもこんな美女が直接遣わされるとは。
鼓動が耳の中で鳴り響く。恥ずかしさと期待がごちゃ混えになって、喉がからからに乾いた。
メイリンはゆっくりと立ち上がり、俺の前に進み出た。
「まずは、陛下の体を確かめさせていただきます。恥ずかしがる必要はございません。私はただの道具……いえ、指南役にすぎませんから」
冷たく言い放つと、彼女は俺の龍袍の紐に指を掛けた。
絹の衣が滑り落ちる音が、妙に大きく響いた。
灯りの下、俺の体は震えていた。まだ誰にも見せたことのない場所が、冷たい空気に晒される。
メイリンは眉一つ動かさず、静かに俺の前に跪いた。
「まずは……ここを、しっかり硬くしていただかねばなりませんね」
彼女の指先が、まるで楽器を調律するように、ゆっくりと這う。
最初は冷たかった指が、だんだん熱を帯びてきて、俺の体は勝手に反応してしまう。
息が荒くなり、膝が震えた。
「……まだ、早いですよ」
メイリンは小さくため息をついた。
「陛下は我慢が足りません。子種は、すぐに零れてしまっては意味がない。もっと、もっと奥底に溜め込んで……そう、限界まで我慢して、濃く、熱く、たっぷりと……」
彼女は立ち上がると、自分の袍の前を静かに開いた。
白い肌が灯りに浮かび、俺の視界が一瞬真っ白になる。
メイリンは俺の肩に手を置き、ゆっくりと跨がってきた。
「動かないでください。私が全部いたしますから」
その瞬間、俺の体は熱に包まれた。
彼女の中は、まるで別世界だった。ぬるりとした熱が、俺の全部を飲み込んでいく。
メイリンは腰を沈めると、一切の余裕を見せずに、深く、強く、杭を打ち込むように動き始めた。
「ん……っ」
俺は思わず声を漏らした。
快感が背筋を駆け上がり、頭が真っ白になる。
「声を上げても構いません。でも、零すのはまだ許しませんよ」
彼女は冷たい目で俺を見下ろしながら、容赦なく腰を振る。
ゆっくりと引き上げて、勢いよく落とす。そのたびに俺の体が跳ね、息が詰まる。
何度も何度も、限界ギリギリまで煽られて、俺はもう泣きそうだった。
「ほら、陛下……もっと我慢なさって。ここに、全部溜め込んで……」
メイリンの息も少しずつ乱れ始めていた。
クールな仮面が、ほんの少しだけ崩れる瞬間。
その隙が、たまらなく愛おしくて、俺は必死に耐えた。
そして、ようやく彼女が小さく頷いたとき、俺は解放された。
熱いものが溢れ、彼女の奥深くに注ぎ込まれる感覚に、全身が震えた。
「……まあ、初めてにしては上出来です」
メイリンは静かに体を離すと、乱れた髪を指で整えた。
「ですが、まだまだです。明日も明後日も、私はここに来ます。陛下が立派な帝王となられるまで、徹底的に鍛え直しますから」
その日から、俺の夜は完全に変わった。
昼の政務など、どうでもよくなった。
朝議の最中も、奏上を聞いている最中も、頭の中はメイリンのことでいっぱいだ。
あの冷たい瞳。あの静かな吐息。あの容赦ない腰使い。
夜が来るたび、俺は宦官に命じてメイリンを呼び出す。
「今夜も、指南を頼む……」
震える声でそう言うと、彼女はいつも同じようにため息をついてから、寝殿に入ってくる。
「……陛下、また甘えたお顔ですね」
メイリンは眉を寄せる。
「甘えは帝王の敵です。私は甘ったれた男が大嫌いです」
そう言いながら、彼女はまた俺の前に跪く。
冷たい言葉とは裏腹に、その手はいつだって優しく、でも容赦なく、俺を限界まで追い詰める。
俺はもう、彼女なしではいられない。
政務を投げ出してでも、夜を待ち焦がれる。
メイリンの鍛錬は厳しいけれど、その奥に確かに感じる温もりだけが、俺の心を繋ぎ止めていた。
この先、何年かかるかわからない。
けれど、いつか彼女が「もう十分です」と微笑んでくれる日まで、俺は甘えたままでいい。
だって、そうやって少しずつ、俺は確実に変わっていっているから。
夜の紫禁城は静かだ。
ただ、宸襟の間だけは、熱い吐息と、甘い懲罰の音で満ちている。


