「一回だけでもシてみない?」


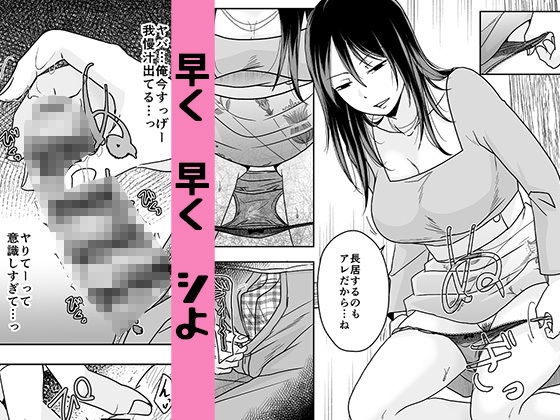
「一回だけでもシてみない?」
========================
一回だけでもシてみない?
同窓会なんて、行かなきゃよかったって後悔したのは、ほんの数分だけだった。
会場を出て、二次会は個室居酒屋。昔のクラスメイトが十人くらい集まって、ビールと焼酎が回る。俺は隅っこでスマホをいじってたんだけど、ふと横を見たら、隣に座ってたのが美咲だった。
美咲は中学のときの同級生で、俺が密かに片思いしてた子。卒業してから二十年近く経つのに、ほとんど変わってない。笑い方がちょっと大人びて、髪が肩まで伸びて、でもあの癖っ毛の感じは昔のままだった。
「ねえ、覚えてる? 中学のとき、俺のこと避けてたよね」
いきなりそんなこと言われて、俺はビールを吹きそうになった。
「避けてたのは俺じゃなくて、お前の方だろ。文化祭のとき、俺が話しかけたら逃げられたじゃん」
「だって恥ずかしかったんだもん」
美咲は笑いながらグラスを傾ける。指輪が光ってた。左手の薬指に、細いプラチナのリング。
「結婚してるんだ?」
「うん。五年目」
「子供は?」
「いないよ。作ろうとしたけど……まあ、いろいろね」
なんか暗い顔したから、俺もつい本音を漏らした。
「俺も同じだよ。嫁とはもう三年くらい、夜の生活がない」
言った瞬間、しまったと思った。でも美咲は目を丸くして、それからくすくす笑い出した。
「え、マジで? 私もだよ。夫、仕事ばっかりでさ。触ってもくれない」
そこから話が変な方向に転がった。
「正直、寂しいよね」
「うん。すっごく」
「たまには……浮気とか、してみたい?」
美咲が小声で言った。俺は心臓が跳ねた。
「一回だけでも、いいからさ」
個室のドアが閉まってる。外の喧騒が遠い。俺たちはもう酔ってる。美咲の手が俺の膝に触れた。熱かった。
トイレに行くふりして、店員に追加の個室を頼んだ。奥の、誰も使ってない部屋。鍵をかける音が妙に大きく響いた。
服の上からでもわかるくらい、美咲の体は熱を帯びてた。俺は震える手でブラウスを脱がせて、ブラジャーのホックを外す。昔、想像してた通りの柔らかさ。美咲は目を閉じて、俺の首に腕を回してきた。
でも、いざそのときになると、俺は情けないことになった。
緊張と興奮が一気にきて、ほんの数回動いただけで、終わってしまった。美咲の中で、びくびくって脈打って、俺は真っ赤になって俯いた。
「ごめん……早すぎた」
美咲は最初、びっくりした顔してた。でもすぐに優しく笑って、俺の頭を胸に引き寄せた。
「いいよ。久しぶりなんだもん」
それから彼女はゆっくりと体をずらして、俺の体を撫で始めた。首筋から胸、腹、そして下。また硬くなってきた俺のを、優しい手で包み込んで、ゆっくり動かしてくれる。
「今度は、もっとゆっくりね」
美咲の声が耳元で囁く。俺はもう何も考えられなくなって、彼女の体に沈んでいった。彼女の吐息が熱くて、指先が俺の背中を這う感触が、たまらなく心地よかった。
どれくらい時間が経っただろう。時計を見たら、もう終電間近。店を出るとき、二人とも妙に冷静な顔してた。でも手を繋いでた。
「このまま帰るの?」
美咲が訊いた。
「嫌だ」
「じゃあ……」
近くに公園があった。深夜の、誰もいない公園。街灯がぼんやり照らすベンチに腰掛けて、またキスした。今度はゆっくり、丁寧に。美咲のスカートをたくし上げて、俺は膝をついた。彼女の太腿が震えてる。夜風が冷たいのに、体は火照ってた。
「ここで……いい?」
「うん。誰も来ないよ」
ベンチに美咲を座らせて、俺は彼女の前に跪いた。ゆっくりと下着をずらして、舌で味わう。美咲は声を殺して、俺の髪を掴んだ。時々小さく震えて、俺の名前を呼ぶ。
「だめ……声が出ちゃう」
「我慢しなくていいよ」
もう我慢できなくなって、俺は立ち上がった。美咲がベンチに手をついて、後ろを向く。俺は腰を抱えて、ゆっくりと繋がった。今度はちゃんと、彼女の中の熱を感じながら、ゆっくり動いた。
夜空に星がちらついてた。遠くで車の音がする。美咲の背中が汗ばんで、俺のシャツに触れる。彼女の息が荒くなって、俺も限界が近づいてた。
「一緒に……いいよ」
美咲が振り返って言った。その顔があまり̔い美しくて、俺は一気に達した。美咲も同時に体を震わせて、俺に寄りかかってきた。
しばらく二人でベンチに座ってた。肩を寄せ合って、夜風に冷やされる。美咲がぽつりと言った。
「明日から、また普通に戻るね」
「うん」
「でも、今日はありがとう」
俺は彼女の手を握った。指輪が冷たかった。
駅まで歩いて、別れた。振り返ったら、美咲も振り返ってた。軽く手を振って、笑った。
家に帰って、風呂に入って、ベッドに横になった。嫁はもう寝てる。俺は天井を見て、今日のことを思い出した。
一回だけ、って言ったけど。
本当は、また会いたいって、思ってる。
多分、美咲も同じだ。
きっと、また連絡が来る。
そのときまで、俺はこの秘密を抱えて、普通の日常を続ける。
でも、心のどこかで、あの公園のベンチの感触と、美咲の吐息の熱さを、ずっと覚えてるだろう。


