「お母さんにはこれぐらいしか出来ないから」
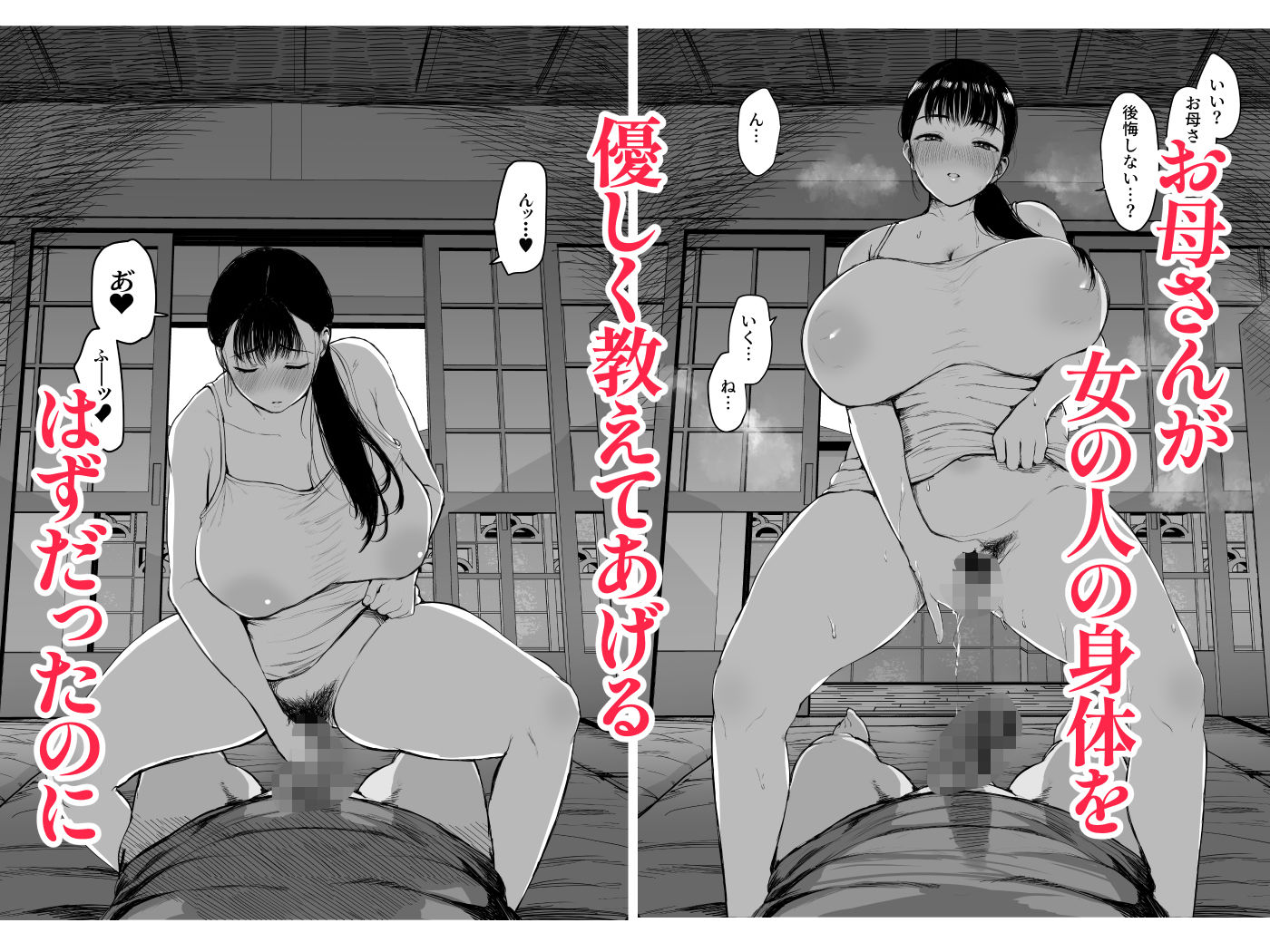


「お母さんにはこれぐらいしか出来ないから」
=================================
夕暮れの光がカーテンの隙間から差し込み、リビングの古いソファをオレンジ色に染めていた。美咲は台所で夕食の支度をしながら、息子の陽太の部屋から漏れる微かな物音に耳を澄ませていた。陽太は二十歳の大学生で、最近は大学にも行かず、部屋に閉じこもりがちだった。美咲はそれが自分のせいだと知っていた。
一ヶ月前、陽太が倒れて病院に運ばれた。診断は脳腫瘍。幸い良性で、手術で取り除ける可能性が高いと言われたが、リスクはゼロではない。医師は「成功率は九十パーセント以上」と繰り返したが、美咲の耳には「残りの十パーセント」が大きく響いた。
その夜、陽太がベッドで美咲に打ち明けた言葉が、今も胸に突き刺さっている。
「お母さん、俺……まだ誰とも、そういうことしたことないんだ」
陽太の声は震えていた。恥ずかしさと、死への恐怖が混じったような響きだった。美咲は息子の手を握りしめた。二十歳にもなって、そんなことを気にしているなんて。けれど、陽太の目には本気の光があった。
「もし手術が失敗したら……このままじゃ、悔いが残る」
美咲は言葉を失った。息子がそんなことを考えるなんて、想像もしていなかった。自分の子が、命の瀬戸際で「経験」を求めている。それがどれほど切実な願いか、母親として痛いほどわかった。
翌朝、美咲は一人で病院へ行った。主治医に相談したわけではない。ただ、陽太のカルテを見ながら、成功率の数字を何度も確認した。九十パーセント。十分な数字だ。でも、残りの十パーセントが、美咲の心を蝕んだ。
帰り道、スーパーの前で立ち止まった。買い物かごを手に持ったまま、夕陽を見上げた。陽太が小さい頃、公園で一緒に遊んだことを思い出した。あの頃は、ただ一緒にいるだけで幸せだった。陽太が成長して、いつか自分の家庭を持つ日が来ると思っていた。でも今、息子は死と向き合っている。
家に帰ると、陽太はリビングでテレビを見ていた。美咲は隣に座った。沈黙が流れた。陽太は母親の顔を見ないようにしていた。
「お母さん、昨日言ったこと……忘れて。変なこと言って、ごめん」
美咲は首を振った。
「陽太の気持ち、ちゃんと聞いてるよ」
陽太の肩が震えた。美咲は息子の背中をそっと撫でた。温かかった。生きている証だった。
夜、美咲は自分の部屋で考え続けた。陽太の願いを叶える方法。普通の母親なら、恋人を紹介するとか、風俗を勧めるかもしれない。でも、美咲にはそんな選択肢はなかった。陽太は手術前で外出もままならない。それに、知らない人との経験が、陽太の心に傷を残すかもしれない。
ふと、鏡に映る自分の姿を見た。四十二歳。まだ若いつもりでいたが、目尻に小さなシワができている。陽太の父親とは離婚して十年以上。男の人と付き合ったこともない。自分の人生は、陽太を中心に回ってきた。
「お母さんには、これぐらいしかできないから」
呟いた言葉が、自分の決意だと気づいた。
翌日、美咲は陽太の部屋をノックした。陽太はベッドで本を読んでいた。
「お母さん、どうしたの?」
美咲は深呼吸した。
「陽太、昨日言ってたこと……お母さんに、任せてくれない?」
陽太の顔が真っ赤になった。
「え、ちょっと待って。お母さん、何言ってるの?」
美咲は微笑んだ。震える声で、でもはっきりと。
「お母さんで、ごめんね。でも、陽太の願いを叶えたいの。他の誰かじゃなくて、お母さんがいい。陽太の初めてを、ちゃんと覚えていてほしいから」
陽太は言葉を失った。美咲は息子の手を握った。
「怖いよね。お母さんも怖い。でも、陽太が生きてくれるなら、どんなことだってする」
陽太の目から涙がこぼれた。美咲は息子を抱きしめた。二十年ぶりの、母親としての抱擁だった。でも、今度は違う意味での温もりだった。
その夜、二人はリビングで向き合った。電気は消して、窓から入る月明かりだけ。美咲は陽太の手を取った。震えていた。自分の手も震えていた。
「ゆっくりでいいよ。陽太が嫌なら、いつでも止めていいから」
陽太は頷いた。美咲は息子の頬に手を当てた。熱かった。自分の唇を、そっと近づけた。初めてのキス。ぎこちなくて、でも優しかった。
美咲は陽太のシャツのボタンを外した。一つずつ、丁寧に。陽太の胸に触れた。心臓の音が聞こえた。速かった。自分の鼓動も同じだった。
「陽太、ここにいるよ。お母さんが、ちゃんと」
陽太は母親の首に腕を回した。美咲は息子の背中を抱いた。温もりが伝わってきた。生きている。陽太は生きている。
二人はソファに横たわった。美咲は陽太の体を優しく撫でた。初めての経験。陽太の反応を確かめながら、ゆっくりと。痛みがないように。怖がらせないように。
「大丈夫? 痛くない?」
陽太は首を振った。目が潤んでいた。でも、微笑んでいた。
「お母さん、ありがとう……」
美咲は涙をこらえた。これは、母親としての最後の贈り物。陽太が生きるための、命の灯火。
朝が来るまで、二人は寄り添っていた。陽太は眠ってしまった。美咲は息子の寝顔を見守った。穏やかだった。手術への不安が、少し和らいでいるように見えた。
手術の日、美咲は陽太の手を握りしめた。陽太は微笑んだ。
「お母さん、俺、絶対生きるから」
美咲は頷いた。
「信じてる。陽太なら、絶対に」
手術は成功した。陽太は目を覚ました。美咲は病室で、息子の手を握り続けた。
「お母さん、俺……生きてる」
美咲は泣いた。陽太も泣いた。二人の涙が、未来を照らした。
それから半年。陽太は大学に復帰した。美咲は相変わらず、一人で暮らしている。でも、時々陽太が帰ってくる。二人で夕食を食べながら、あの夜のことを話すことはない。でも、目が合うたびに、互いの存在が確かなものだと感じる。
美咲は思う。あの決断が正しかったかどうかは、わからない。でも、陽太が生きている。それだけで、十分だった。
「お母さんには、これぐらいしかできないから」
あの夜の言葉は、今も美咲の胸に残っている。でも、もう謝る必要はない。陽太は生きて、母親の愛を胸に、新しい人生を歩き始めたから。


