「幼馴染は繋がりたい〜三人は一緒編〜」
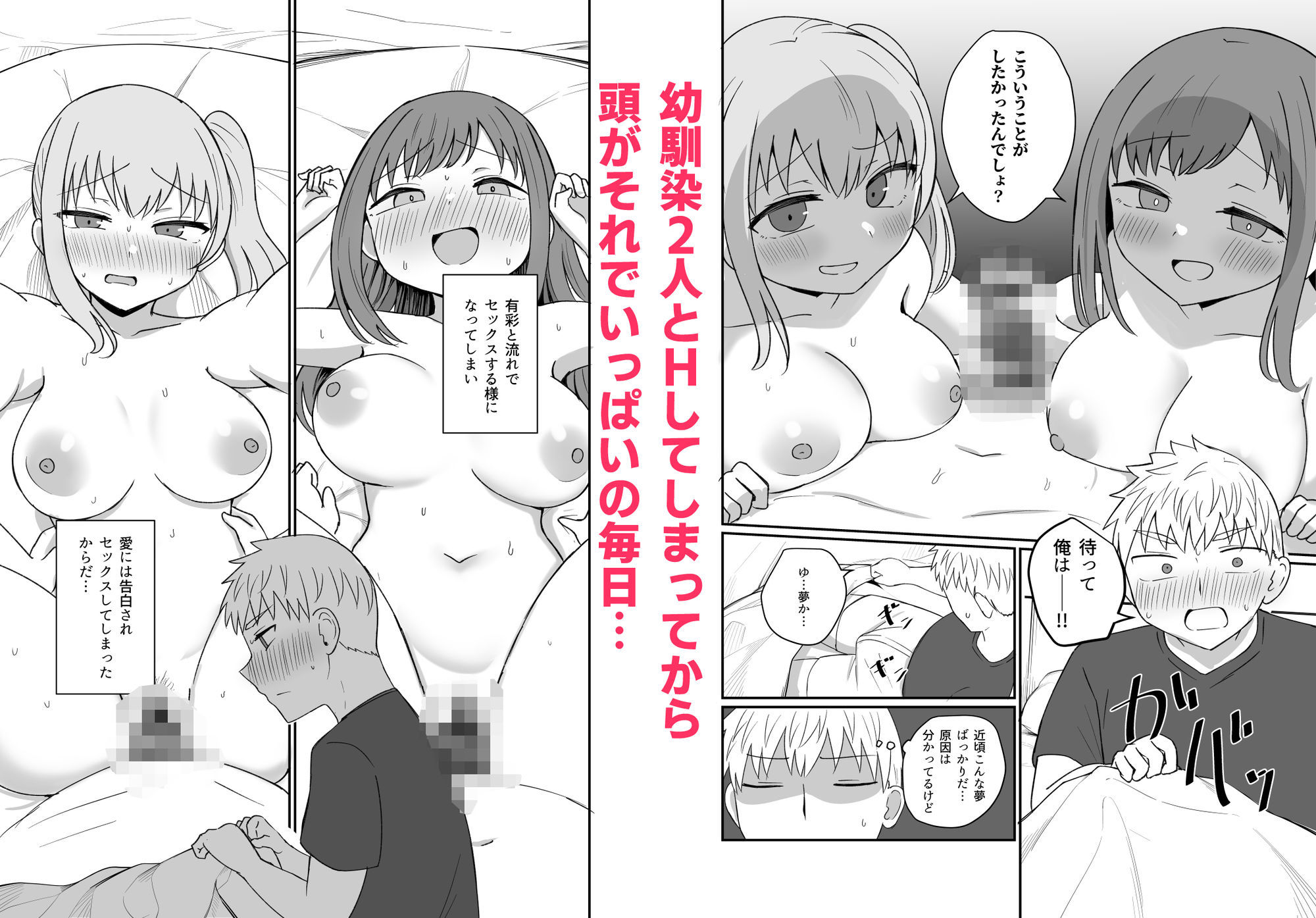
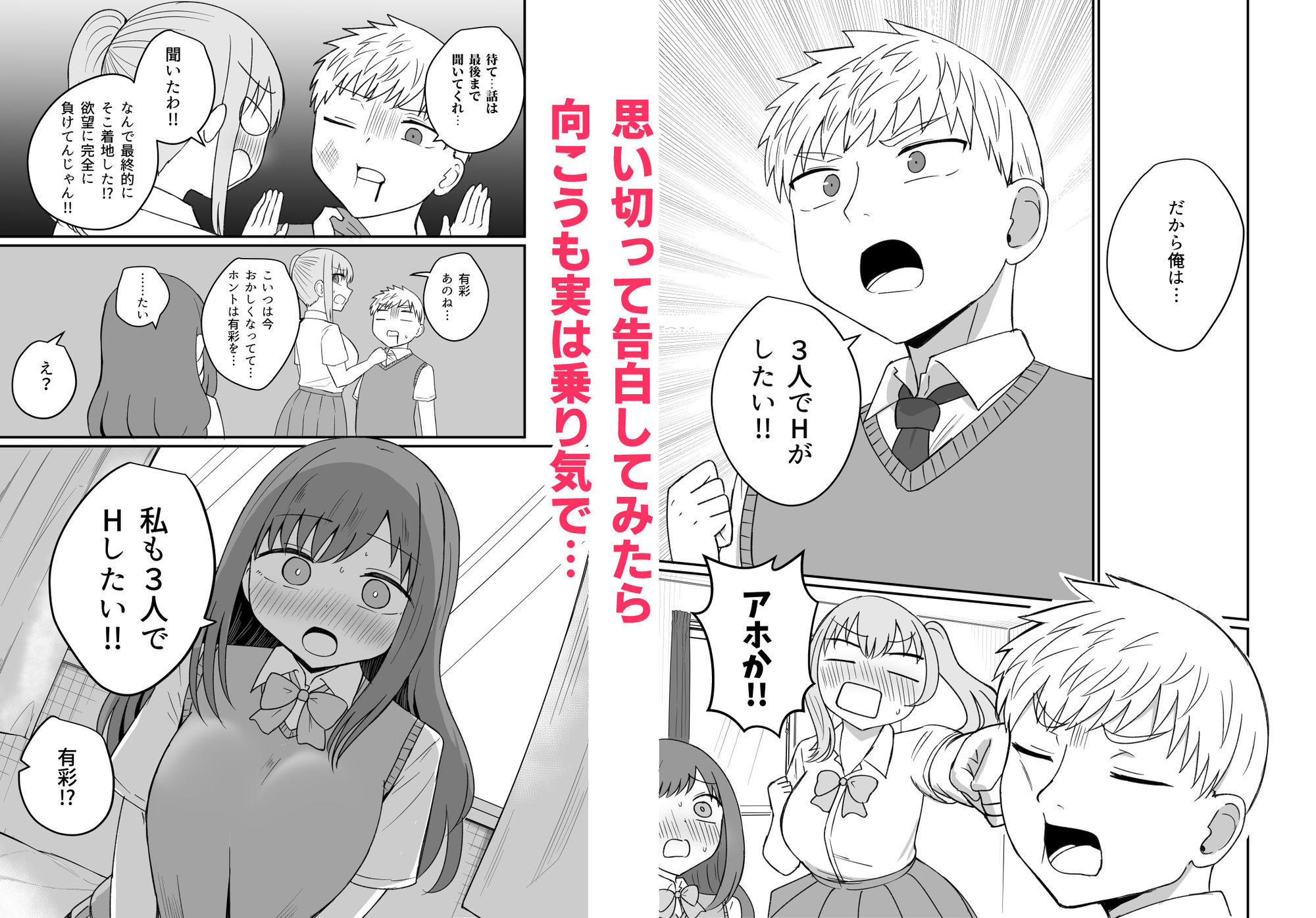

「幼馴染は繋がりたい〜三人は一緒編〜」
==========================
夏の終わり、蝉の声がうるさすぎて頭が痛くなるような日だった。俺たち三人はいつもの河原でダラダラしてた。健太郎、有彩、愛。物心ついた頃からの幼馴染で、二十歳過ぎたいまも変わらず一緒にいる。ビール片手に馬鹿話して、流れで誰かの家に転がり込むのがいつものパターン。その日は有彩の親が旅行で留守だったから、夜遅くまで有彩の部屋で飲んでた。冷房効きすぎて寒いくらいで、みんな酔いが回ってくると妙なテンションになる。有彩が「ねえ、キスしたことある?」とか急に言い出して、愛が「バカ笑いしながら「あるに決まってるじゃん」とか返して。そっから話はどんどん下品になって、気づいたら俺と有彩がキスしてた。最初は冗談のつもりだったはずなのに、有彩の唇が柔らかすぎて頭真っ白になった。愛が横で「え、マジで?」って驚いてる声が遠くに聞こえて、それでも俺は有彩を押し倒してた。服の上から胸触ったら有彩が小さく喘いで、俺の中で何かが切れた。愛は最初固まってたけど、すぐに「私も混ぜてよ」って笑いながら寄ってきて。三人でベッドに転がり込んで、服を脱がせ合って、汗だくになって絡み合った。有彩の腰が細くて、愛の胸が思ったより大きくて、俺はだけたシャツからこぼれてて。俺は有彩の中に入ったとき、ずっと好きだった子を抱いてるって実感が湧いて震えた。でも愛が後ろから俺の首に腕回して耳元で「私も欲しい」って囁いた瞬間、頭の中がぐちゃぐちゃになった。結局その夜は三人で朝までやって、疲れ果てて重なり合ったまま寝た。朝起きたら有彩が俺の胸に顔埋めてて、愛が俺の腕枕にして寝息立ててて、なんか現実味がなかった。それから一週間くらい、俺は有彩のことで頭がいっぱいだったはずなのに、愛のこともチラチラ思い出して集中できなかった。有彩は昔から好きだった。小学の頃からずっと。でもあの夜、愛の身体の感触とか、甘ったるい声とか、全部が頭にこびりついて離れない。ある日、三人でまた飲みに行った。いつもの居酒屋の個室で、ビールジョッキ並べてるときに、俺は唐突に口を開いた。「……なあ、俺たち、このまま三人で付き合わないか?」有彩がビール吹き出しそうになって、愛が目を丸くして俺を見てる。「は? どういうこと?」有彩が笑いながら聞いてきたけど、目が本気だった。「いや、そのまんまの意味。あの夜からさ、俺、有彩のこと好きだし、でも愛のことだって……同じくらい気になってる。どっちか選べって言われたら無理だわ。正直、二人とも欲しい」愛が「ちょっと待って」とか言いながら顔赤くして、でもニヤニヤしてる。有彩は最初ムッとしてたけど、だんだん黙って俺のこと見てた。「有彩、お前はどう思う? 俺、昔からお前が好きだったのは本当だよ。でも愛も……あの夜からずっと頭から離れない」有彩が小さくため息ついて、ジョッキをテーブルに置いた。「……私も、実は愛のこと可愛いって思ってる。昔から。健太郎取られるの嫌だったけど、あの夜は正直、愛が隣にいるの気持ちよかった」愛が「え、私のこと?」って驚いた顔して、それから急に恥ずかしそうに俯いた。「私も……二人とも好きだよ。健太郎のことずっと見てたし、有彩のことだって、女の子としてドキドキしてたし」三人で顔見合わせて、なんか変な沈黙が流れた。でもそれが嫌な沈黙じゃなくて、むしろ熱を帯びたような。俺が立ち上がって、有彩と愛の手を握った。「じゃあ決まりだな。これからも三人で、ずっと一緒にいようぜ。恋人同士ってことで」有彩が「バカみたい……」って呟きながらも、でも嬉しそうに笑った。愛が「変態三人組だね」って言いながら俺の腕に抱きついてきて。それから俺たちは本当に三人で付き合い始めた。普通のカップルみたいにデートしたり、でも三人で手を繋いで歩いたり、夜は三人で同じベッドに入って、朝まで離れなかった。有彩の甘い匂いと、愛の柔らかい肌と、俺はその狭間で溺れていくような毎日だった。誰かに変だと言われてもいい。三人だけの世界が、俺には何より大事だったから。


